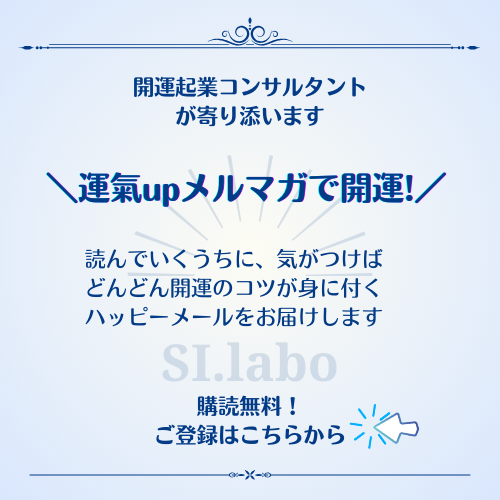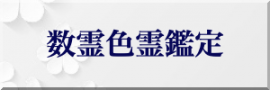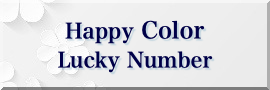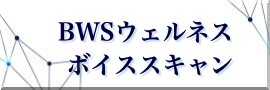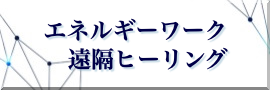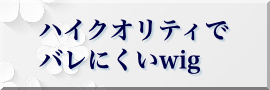精霊馬でお出迎え

子供の頃、お盆になると、親戚の面々が本家に集まり、先祖の供養をしました。
本家では、お仏壇とは別に、精霊棚というのが設置され、位牌や香炉・お鈴・灯明立てなどはそちらに移し、そのタイミングでお仏壇の中を綺麗にお掃除します。
精霊棚には、まこもというゴザの上に、果物などのお供えと、ナスやキュウリで作られた精霊馬を内側に向けて並べ、迎え火は13日に、ご先祖様方が来られる道標として、ほうろくにおがらを焚いてお迎えします。
馬や牛の背中にはそうめんがかけてあり、「水の子」と言って、ナスやキュウリをさいの目に刻んで、洗ったお米を少し混ぜたものを、あの世で上に苦しんで乾いた喉に少しでもい通りやすいようにと、蓮の葉に乗せてお供えします。
先祖の数のご飯やお供えには、各々が、柳の葉で水をシャシャってかけて読経します。
先祖の数が多いので、お彼岸やお盆の時には、ずら〜っと御霊供膳(おぶくぜん)が並んでいた。
今思えば、あの時代の本家のお嫁さん、大変だったことと思います。

「精霊馬(しょうりょううま、しょうろうば)」とは、お盆の時期にご先祖様の霊がこの世に戻ってくる時の送迎用の乗り物としてお供えする、キュウリやナスで作られた飾り物のこと。主に日本の仏教行事である、お盆に用いられる。
キュウリで作る馬→早く来れるように
四本の割り箸や爪楊枝を足にして刺し、キュウリを胴体に見立てます。
馬は足が速いとされ、ご先祖様が早く帰ってこられるようにとの願いが込められています。ナスで作る牛→ゆっくり帰ってね
同様に、ナスに割り箸などを刺して牛を作ります。
牛は歩みが遅いため、「名残惜しむようにゆっくりあの世へ戻ってほしい」という願いが込められます。お盆明けには、精霊送りと言って、16日の夕方に送り火を焚いて、川や海に流す、あるいは塩で清めて処分するなど。
地域によって方法が異なりますし、行政の法令などにより、気軽に川に流したりはできない場合もあります。
クーラーが、どこの家庭にでもほぼ設置してある今と比べて、それほどなかった時代、団扇や扇子で仰ぐのが普通で、自然の風で十分涼しくて、クーラーというモノが不要だった時代。
そうだ、扇風機がありました。
黒いごっつい鉄製のやつで、スイッチを入れると、結構派手目な音量で風が流れ、扇風機自ら動いて移動していました、ダダダダって。
実はこれ、子供心にウルトラ怖かった記憶は、今でもはっきり覚えています。

そして、縁側で、採れたてスイカやとうもろこしをほおばり、夜は星を眺めたり。。。
無数の星がはっきり見えていた。
子供の頃はそーいったイベントの集まりがイヤで、親に連れられて仕方なく参加していましたし、のどかな田舎の風情が嫌だと思ってたけど、歳を重ねたせいなのか時代がそう思わせるのか…
今思うと、良かったな〜、いい時代だったな〜、しみじみ。
少し早いですけど、お盆の思い出を書いてみました。
ご先祖様方が遊びに来られ、楽しく過ごしていただけるといいな^^
2025年8月12日
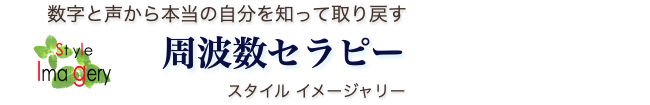
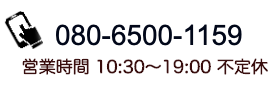
 カラー&イメージコンサルティング
カラー&イメージコンサルティング